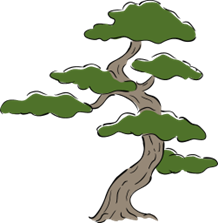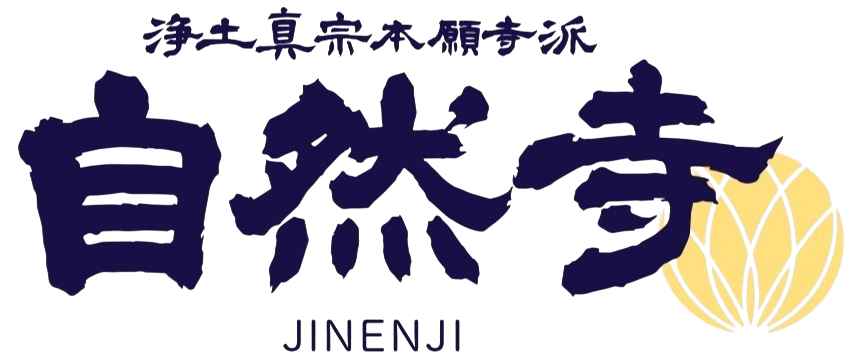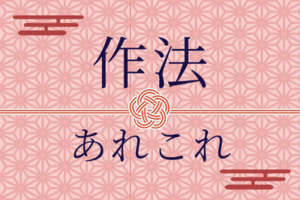西本願寺にて常例布教の講師として出講させていただきました。
緊張感の中、前門さまの御前でご法話をさせていただきました。
十二月十日から十三日まで、ご本山 西本願寺にて常例布教の講師として出講させていただきました。毎朝六時に始まる晨朝勤行(じんじょうごんぎょう)は、十二月の凛とした空気の中で、多くの参詣者とご一緒に正信偈(しょうしんげ)のお勤めをいたします。最終日の朝、前門さま(二十四代大谷光真 前御門主)が御出座されました。ここ数年、前門さまは足を悪くされ杖をつかれています。この日も杖を持って御出座なさいましたが、よくよく拝見すると、杖の先端は地面から浮いています。…胸を打たれました。
ご本山・西本願寺や築地本願寺のお内陣(仏さまをご安置する領域)の床は漆で仕上げてあり、薄暗い灯りでも自身が映るほどピカピカに磨き上げられています。それを長持ちさせるために、お内陣に入る際は必ず綿の白足袋を履いて入るように指導されます。伸縮性のある化繊の足袋や靴下もダメ。スリッパなど履物を履いて入ることも厳禁です。仏さまをご安置する領域はそれほど厳格に、丁寧に接することを求められるのです。
前門さまは本願寺の前御住職でありますから、自らのお寺で杖をついて歩かれ、そのままお内陣に出られたとしても、誰も咎めることはありません。これまで六十年近く正座され、晨朝のお勤めに始まり、様々な法要を真摯な姿勢で勤めてこられたお姿を皆知っています。それなのに、お内陣では杖を地面に付けることなくゆっくりと歩を進められるそのお姿は、このお寺を守ってきた「誇り」阿弥陀さま親鸞さまをご安置するお堂を大切に思う 「お敬い」のお心がそのまま顕れているのだと思い知らされました。その前門さまの御前でご法話をさせていただく…この緊張感、伝わりますでしょうか?

聴聞とは耳で聞いて頭で理解するようなものではない。
このようなお話をさせていただきました。
浄土真宗では「聴聞」を大切にいたします。これはつまり、仏さまのお話を聞くということです。第八代蓮如上人は「仏法はただ聴聞にきはまれり」と仰せです。ですから法話の際は居眠りなどせず、メモを取ったりして一生懸命に記憶するということがいつしか聞法の姿勢となっていました。しかし蓮如上人のお言葉の前にはこうあります。「至りてかたきは石なり、至りてやはらかなるは水なり、水よく石を穿つ(うがつ)、心源もし徹しなば菩提の覚道なにごとか成ぜざらんといへる古き詞あり。いかに不信なりとも、聴聞を心に入れまうさば、御慈悲にて候ふあひだ、信をうべきなり。ただ、仏法は聴聞にきはまることなりと云々」
至りて…きわめて
穿つ…穴をあける つらぬく
心源…心の本源 心の底
菩提の覚道…仏のさとり
つらい事・悲しい事があって「どうにかすくわれたい」と願っているうちは心がきわめて固く仏のさとりを聞き受けることは難しい。しかしその心のまま、お寺に参り仏さまのお話を全身で受け止めると、仏さまのお慈悲がいつしかこの身を貫き、お慈悲で満ち溢れてゆくのです と仰せです。
つまり、聴聞とは耳で聞いて頭で理解するようなものではない。雨が乾いた地面にスッと染み込むように、心を柔らかく「わたしは…」というものの見方を一旦横に置き、仏さまのお慈悲をそのまま全身でいただく。これが聴聞だと蓮如上人は仰せなのです。
私は「言うことを聞きなさい」と言われると聞きたくなくなります(笑)親であっても先生であっても上司であってもです。阿弥陀さまはそんな天邪鬼な私の本性を見抜かれ、聞け・覚えろ・でないとすくわれないとは申されませんでした。母の腕に抱かれる赤子のように、ただそこに身をゆだね、「まかせる」という姿勢が聴聞の極意だとお聞かせいただくのです。 そうでなければ一切衆生(生きとし生けるあらゆるいのち)をすくう仏とならないと阿弥陀さまは仰せです。他の誰でもない、この私一人をおすくいくださる仏さまがご一緒の今日でありました。
仏さまは いつも・ここに・ともに